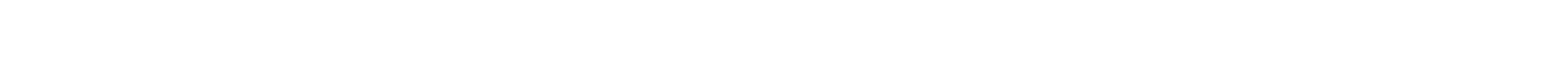〈ダイジェスト〉
「立地」より「客層」を選ぶ調剤薬局
病院に足を運びにくい高齢者が増えています。介護施設に入居したり、在宅療養したりする高齢者も増えています。
薬をもらいに出向くのが大変なだけではなく、いくつかの病気をかかえ、もらう薬が多くなる人もいます。
複数の病院から何種類もの薬をもらうと、同じ効能の薬をのむ人がいる一方、多数の薬を管理できず、のみ切らない人もいます。
患者一人ひとりの病状を把握している家族や、かかりつけの医者がいればいいのですが、現状は本人まかせ。
その状況を打開しようと、患者一人ひとりとの関係性を深めている会社が、『わに薬局』を展開している有限会社メディカルブレーンです。
平成9年、琵琶湖の西岸、大津市の和邇(わに)に一店目を開いた塩飽勝美(しわくかつみ)社長は現在、滋賀県と京都府に計7店の調剤薬局を展開。約300にのぼる医療機関から処方箋を受け付けています。
居宅介護支援事業所のほか、福祉用具のレンタルや環境事業においてもお客の支持を高めています。
店舗ごとに目標を設定していますが、どの店も毎年、目標を達成。お客の数である患者数の伸びは過去5年、平均して110パーセント前後を達成しています。
診療報酬明細書、すなわちレセプト件数も前年比で1割強という増え方。お客が増えているもっとも確かな裏づけと言えます。
外来患者数が多い大規模病院の門前に店舗を構えるのが調剤薬局の理想とされていますが、メディカルブレーンは正反対。「開業医の前がいい」と塩飽社長は次のように言います。

高齢者のなかには、かかえる症状の違いから複数の病院へ通う人がいます。それぞれの病院で処方箋をもらい、それぞれ異なる薬局で薬をもらいます。
どんな薬をもらい、服用しているかを記録する「お薬手帳」がありますが、高齢者には薬局ごとにお薬手帳を使い分けている人がいるため、複数の薬をもらっていることが発覚しません。
重複してのんでいる薬を管理してあげる人がいない。そんな状況を塩飽社長はだまって見ていられません。

それを追求して薬局を展開してきました。
本当にお客の役に立つ調剤薬局を追い求めてきた結果、7店目は在宅患者専門の薬局をつくったほどです。
在宅患者や介護施設の入居者は、薬局に出向いたり薬剤師に相談したりする機会がほとんどありません。来店が難しいなら、こちらから訪問する。塩飽社長のその考えが、さらにお客の数を増やしています。
自社にとって最適の客層はだれか。その客層に最適のサービスを提供するには、どんなやり方が考えられるのか。戦わずして同業他社よりお客を増やすには、どんな経営を貫くべきか。
それらを教えてくれるのが、「お客が増える! No.56 有限会社メディカルブレーン」の事例です。
>>トップページに戻る