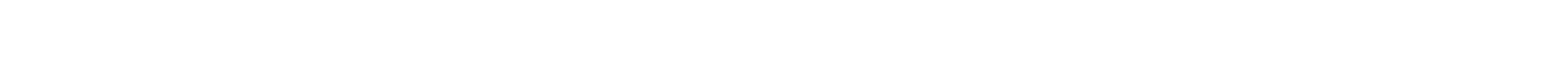志をもって地域おこしに取り組み始めたものの、「思いの強さだけではうまくいかない」と頓挫する例に事欠きません。
“食っていける”だけの仕組みをつくることができたケースのみ、地域おこしは軌道に乗るようです。
かたくなに高品質を追求し、商品力の高さで支持を得ながら、それでも「やはり商品は3分」と自戒する戦略社長の事例です。
〈ダイジェスト〉

沖縄の方言で「酸っぱい」ことを「シー」と言い、「クヮーサー」は「食べさせる」という意味があるそうです。つまり、酸っぱい食べ物がシークヮーサーということになります。
名護市の勝山地区を勝山区と呼びますが、勝山区では山の斜面を利用して50戸ほどの農家がシークヮーサーを栽培してきました。
このシークヮーサーで地域起こしをしようと立ち上がったのが、現在、有限会社勝山シークヮーサーで代表を務める山川良勝さんたち、地元の農家でした。
平成13年に結成した勝山シークヮーサー出荷組合を発展させ、「農業生産法人 有限会社勝山シークヮーサー」を立ち上げたのです。
限界集落と化していた勝山の過疎化を食い止めたい。地域の宝である農産物を活かし、地域で働ける加工場を造り、雇用を生み出したい。農家の所得を増やし、地域を元気にしたい。そう願っての事業です。
沖縄本島北部のやんばる地方には、当たり前のように自生していたシークヮーサーは、沖縄の言葉で「チュファーラ一銭」、訳すと「おなかいっぱい食べてもわずか一銭」と言われるほど価格が安い果物でした。
ところが近年、疲労回復や肥満防止、美容や美肌、動脈硬化や高血圧の予防に効果があるという評価が高まり、全国的な人気が出ました。勝山シークヮーサーも販路を拡大させることができました。
ノビレチンやヘスぺリジンといった機能性成分が多く含まれていることがわかり、飲料以外にもさまざまな食品に使われることで市場を広げてきました。

同業他社にはシークヮーサー以外の柑橘類を混ぜ合わせた商品を出荷するところも多く、しだいにシークヮーサーそのものの評判も落ちていきます。
2005年(平成17年)、ピークを迎えたシークヮーサー市場は一気にしぼみ始めますが、勝山シークヮーサーは生き残りました。生き残ったどころか出荷量も販売先も年々増えています。
・他社が売上増大を目論み、商品数を増やすなか、入手できる地元産の原材料に見合った商品アイテムにとどめたからです。
・他社が営業網を発展させ、全国展開を進めるなか、本土での営業を縮小し、沖縄の一部に営業地域を絞ったからです。
・他社が客層を広げるなか、勝山の契約農場で収穫した地場100パーセントのシークヮーサーでなければ買わないと言ってくれるお客を増やしてきたからです。
農家という原材料を生産してくれる取引先があり、加工、販売する勝山シークヮーサーがあり、商品の品質や企業姿勢に高い価値を感じてくれるお客によってビジネスが成り立っています。
仕入れ先、自社、お客。形がある商品であれ、お金をいただく業務であれ、技術を提供するサービスであれ、中小企業が直面する問題に立ち向かいながら、お客を増やしてきた事例が№49、「農業生産法人 有限会社勝山シークヮーサー」です。
>>トップページに戻る